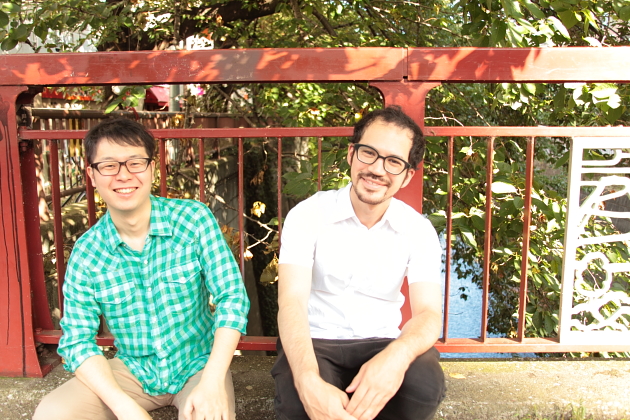大山エンリコイサム(美術家)× 平本正宏 対談
収録日:2012年8月5日
収録地:中目黒
対談場所:リゴレット RIGOLETTO SHORT HILLS 中目黒
撮影:moco
<グラフィティ・レタリングの造形的可能性>
平本 大山くんと出会ったのは、ぼくらが大学院のときだよね。Tekna TOKYOのデザインもしてくれている建築家の鈴木隆史くんとかと一緒に。
大山 ぼくが芸大の大学院に入学したのが2007年だからね。少なくとも2008年にはもう会っていたと思う。
平本 というともう4、5年は経っているんだね。早いね。
学生のときから知っているというのもあるけど、出会ったときからグラフィティの研究やそれを起源とした美術作品を制作していて、それが最近とても評価されているでしょ。COMME des GARÇONSのアートワークや京都のホテル・アンテルームの壁画など、大山くんの作品がいろいろな場所に広がっていく印象を受けている。

COMME des GARÇONS パリ・コレクション2012春夏用のアートワーク。Photo by Kou Miyama
ただ単にグラフィティをかいていくというんじゃなくて、それを根源にもちながらも本来のグラフィティでは想像されないようなさまざまな展開をしていると思う。それが結果として多くの刺激的なコラボレーションの可能性を提示したり、美術作品としてのグラフィティの可能性を示しているわけじゃない? その大山くんならではの自分の活動に対する考えというか、思いを知りたいなと。
あと、音楽に対する姿勢や音楽との関係をどう考えているかも聞きたいところなんだよね。ミュージシャンやDJがいて音楽を流して、その曲や空間からインスピレーションを受けてかいていくライブペインティングは、グラフィティに限らずよくあるでしょ。そういう形での音楽との交わりじゃなく、もし音楽との共同制作の可能性を考えていたらその構想を聞いてみたいと思っている。もちろん、今日の対談のなかで新しいアイディアが出て来たらそれはもっと面白いと思うし。
大山 自分の活動を文脈化することも大切だと思っていて、作家としての制作と平行して文筆業もやっている。まず自分の立場を簡単に説明しておくと、ぼくの創作はグラフィティにとても影響を受けているのだけど、ぼく自身がグラフィティの正当な実践者かというとそうではない。グラフィティというのはひとつの文化なんだよね。その文化の「内側」にいるコミュニティの成員かというとそうでもないし、かといってアカデミシャンが参与観察的にサブカルチャーのなかへダイブしていくような「外部」からの視線でやっているかというと、そういうわけでもない。言わばどっちつかずの、境界線上にいる感じかな。むかしはそれで、居場所がなくて苦しむこともあったけど、今は逆にそういう自分の立場だから言えることやできることもあるのかなという感じで、肯定的に捉えている。
そのうえでグラフィティについて考えていくと、まず基本的には、ストリートにスプレーやマーカーを使って名前をかいていくという行為なのね。都市というメディアと名前というモチーフの結びつきが重要。公共の場に名前をかくことで、自分の存在を人びとに主張することが動機だから。それから、多くの場合は許可を得ずにゲリラ的にやるので違法行為。法律的には器物損壊になる。そうするとグラフィティに対する意味づけとして、政治闘争的な解釈の仕方がわかりやすくなるんだよね。国家・警察権力へのレジスタンスであったり、社会で発言権を持たない人びとの匿名的な声として捉えると、理解しやすい。だからグラフィティに対する批評的解釈は、文化左翼的な見方のものが多くなる。
ただそのような見方は往々にして、グラフィティという文化を外部から眺めている可能性が高い。グラフィティを一般社会との関係という位相で捉えているとも言えるね。もちろん間違ってはいないんだけど、ぼくはそれだけではないと思っていて、コミュニティの内側にはまた別の価値体系があったりもする。たとえばグラフィティの読み解き方を知っていれば、文字の複雑な崩し方や造形がユニークな発達をしていて、そこに豊かなヴィジュアル・ランゲージ(視覚言語)が詰まっていることがわかる。にも関わらず、それを読み解くにはかなりハイコンテクストなリテラシーが必要なので、その豊かさは一般的にはなかなか気づかれにくい。権力に対するストリートからの抵抗という、60年代から連綿とつづく文化左翼の物語に回収するほうが説明しやすいわけで、今のところ文化産業におけるグラフィティの役回りはそういう位置づけになってしまう節があるんだよね。
ぼくとしてはヴィジュアル・ランゲージとしてのグラフィティにスポットライトを当てたいと思っている。グラフィティは名前としてかかれるから、その造形はデザインされた文字の組み合わせ(レタリング)なのだけど、この「名前」というのがここで問題になる。いま言ったように、まず公共空間に名前をかくという行為は政治闘争的な解釈を呼びこみやすい。それから名前=文字であるということは、それが「読める/読めない」「リテラシーがある/ない」というかたちでコミュニティ内外の温度差をどうしても引きずってしまう。そして造形的にも、グラフィティの独特なデザイン性が、結局は文字型という外枠に規制されてしまうのね。そう考えていくと、名前であることがいろいろな意味で足かせになっていることが分かると思う。だからぼくのやっていることは、グラフィティ・レタリングから文字型をはずし、クイックターンという描線の運動だけを取り出してきて反復することで、抽象的なモチーフへと再構成していくという作業。そのモチーフをクイックターン・ストラクチャー(Quick Turn Structure、以下QTS)と呼んでいる。

クイックターン・ストラクチャーの絵画作品。
<FFIGURATI #17>、2011年、Photo by Takahiro Tsushima
QTSは抽象的な描線運動の「プロセス」なので「名前」ではない。そうするとまず、読める/読めないというリテラシーの問題がなくなり、コミュニティの内部/外部という構造も蒸発する。たとえばバンクシーなんかは、ストリートアートと現代美術のリテラシーのギャップ自体をコンテクストゲームとして、パズルをはめるみたいな感じでパフォーマティブに主題化していくわけだけど、ぼくの場合はそもそもリテラシーが要請されない地平で、濃密なクイックターンの描線運動を感覚器官的に感じとって欲しいわけ。音楽のメタファーで言えば、ゲーム性やメッセージ性の強いラップやフォーク・ミュージックではなく、エレクトロニクスで音を増幅させたりする音響系やアブストラクト・ヒップホップに近いのかもしれないね。
それからQTSは、ストリートに名前をかくというグラフィティのミッションから切り離されているので、都市空間という単一のメディアに縛られる必要はない。さっき、ぼくの作品がいろいろなところに広がっていく印象ということを言ってくれたけど、まさに特定のメディアに根を下ろさず、さまざまなメディアを横断しながら拡散していくというのがQTSなのね。グラフィティの場合はストリートのいろいろなところに拡散的に名前をかき残していく一方で、キャンバスにかいたらもうグラフィティではないというような、ストリート原理主義みたいなところがある。他方でQTSは、ストリートでも壁画でもキャンバスでもCOMME des GARÇONSの洋服でも、いろいろなメディアを拡散的に横断していくというイメージがあるんだよね。
平本 グラフィティの場合は、都市空間という単一のメディアのなかで拡散的に広がっていくけど、QTSはさまざまなメディアそのものを拡散的に横断していくということかな。
大山 そう。名前であるグラフィティ・レタリングをQTSに抽象化することで、それをめぐる拡散性も都市空間に限定されずより多層的になるという感じかな。ただ、なんの軋轢もなくスムーズにメディアを横断していくというよりは、むしろ拡散しながら摩擦を引き起こしていくイメージがあって。だから、伝播先のメディアが持つ特性との拮抗関係が大事だと思っている。この拮抗関係はコンセプチュアルな場合もあるし、即物的な場合もある。たとえば「あいちトリエンナーレ2010」ではビルの壁面にかいたのだけど、グリッド状にならぶ窓のうち、上にかいてよいものとそうでないものがあって、それがQTSの運動に働きかける物理的な制約としてあった。その制約とQTSがネゴシエーションすることで、その条件のなかでしか生まれない造形ができてくる。COMME des GARÇONSのときも、川久保玲さんの描いているコレクションのイメージや洋服のかたち、素材の質感などが前提として強烈にあったしね。そのときしかありえない条件のなかにQTSを放りこむことで、新しい表情や変化が生まれることをつねに期待しているかな。

クイックターン・ストラクチャーの壁画作品。
<Choja-Machi Mural Project>(あいちトリエンナーレ2010)、2010年、Photo by Takahiro Tsushima